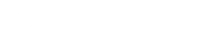遺言の種類と作成方式について
遺言の種類と作成方式について
 2025/08/1
2025/08/1

遺言は、法律で規定されている方式でおこなう必要があります。今回は、遺言の種類と作成方式についてご説明します。
日本の民法における遺言には、以下の3種類があります。
① 自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する方式です。メリットとしては、費用がかからず単独で作成できる点、秘密性が高い点などが挙げられます。デメリットとしては、法的要件に不備があった場合に遺言が無効になる可能性や、紛失のリスク、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要である点が挙げられます(後述する法務局の保管制度利用時を除きます)。
② 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者の口述に基づき公証人が作成します。作成時には証人2名が立ち会います。法的に最も安全で、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。ただしデメリットとして、費用や手間がかかる点が挙げられます。
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書を封印し、公証人と証人2名の前で提出する方式です。内容の秘密性を保ちつつ、公証人の関与がある点がメリットとして挙げられますが、自筆証書遺言と同様に検認が必要で、あまり利用はされていません。
また、法務局による自筆証書遺言の保管制度(遺言書保管制度)があります。費用は3900円で、検認も不要になるため、費用や相続人の手間を抑えることができます。
なお、遺言者ご自身が法務局まで出向く必要があること、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書が必要となることなど、利用上の制約がありますので注意が必要です。また、遺言の内容についての有効性は審査されないため、相続トラブルを予防するためには専門家の助言を受けることをお勧めします。
執筆者 司法書士 日野友季
専門家へのお問い合わせはこちら
097-532-7055