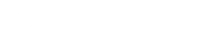曖昧な遺言はトラブルのもと(後編)
曖昧な遺言はトラブルのもと(後編)
 2025/04/3
2025/04/3

前編では、「私Aは、不動産を妻Bに譲る。妻Bが死亡した後は、当該不動産は弟Cに譲る。」という遺言書がある場合はどのように解釈するのかについて、最高裁の判決を引用しました。
前編の判決をかみ砕いて説明すると、
①妻に遺贈したのであり、「弟に譲る」の部分は単なる妻への希望を述べたにすぎず、法的な拘束力はない。
②妻への遺贈は、妻が死亡した時には、弟に所有権を移転する義務を妻に負担させた遺贈である。
③妻への遺贈は、妻が不動産を所有したまま死亡した時には、弟に所有権が移転するという、「後継ぎ遺贈」と呼ばれる遺贈である。
④弟に遺贈したのであり、妻には不動産を使う権利等を与えたにすぎず、妻による不動産の処分は禁止されている。
のような解釈をする余地がある、となります。
しかし、遺言を実現するためには、どの解釈が正しいのか確定する必要がありますので、最高裁は次のように解釈するとしました。
「遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたつても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」
曖昧な遺言を作成すると、意図が伝わらず、かえって争いの種になってしまうこともあるため、遺言書の作成は専門家に相談することをおすすめします。
執筆者 司法書士 岩井將
専門家へのお問い合わせはこちら
097-532-7055